| profile | exhibition | decoration | detail | message | informartion |
|
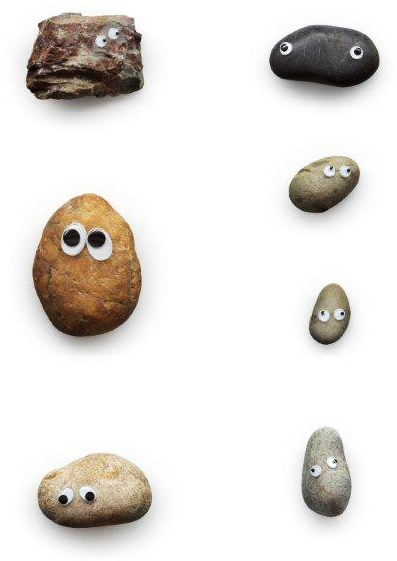 |
高校生の頃は、絵が好きで美大受験を考えていた。種々の理由から国文学を専攻し卒業したが、私の周辺では常に様々なアートシーンの展開が感じられていた。画家になる夢と平行して趣味として習っていた西洋刺繍は、大学を卒業する頃には自分にとっての表現手段の一部にまでなりはじめていた。工芸的な小世界でしかない刺繍で、アートとしての展開が出来ないか。アートとしての刺繍展開をしている先人はいないのだろうか。アンテナを張り巡らし誰かれとなく熱心に話しても、シシュウと聴いて詩集を思い浮かべ刺繍をイメージする人は少なかった。見つからない。情報がない。1976年ヨーロッパに飛んだ。刺繍材料輸入会社を経営する人の好意で、輸入先の会社を訪問する旅に同行させてもらったのだ。何か手掛りが欲しかった。ドイツ、スイス、フランス、イギリスと回り帰国の日が迫っても、アーティスティツクな刺繍には全く出会えなかった。何の情報も得られなかった。帰国前夜、ロンドンのレストランで、「それならゴールドスミスカレッジにある。」と知った。もう一日早く判っていれば、この目で大学を確認することも出来たのだが、それは叶わずに帰国した。帰国後、ブリティシュカウンシルに何度も足を運び調べた。大学リストに名前を見つける事は出来ても、その内容は何一つ判らず結局、手紙で直接問い合わせることにした。ゴールドスミスカレッジは、ロンドン大学という大きな傘の下にある沢山のカレッジの中の一つで、芸術学部の中にテキスタイル&エンブロイダリーコースがある事がわかった。大学を卒業しB.A.を持っている事と言う受験資格はクリアーしていた。トランクに受験の為に準備した日本刺繍作品をぎっしり詰めて渡英した。最初の手紙を投函してから二年余りの歳月が流れていた。身の回りの物を詰め込むスペースは無く、着のみ着のまま状態での出発だった。 ゴールドスミスカレッジは、総合大学であらゆる学科が存在し、夜間はアダルトスクールとして社会人教育のために校舎は使われ、マンモス大学特有の騒々とした落ち着かない大学だった。そんな本校からバスで20分~30分離れた静かな場所に、ミラードビルディングがある。この古い煉瓦造りの建物が芸術学部だった。全ての学生の顔が認識できる小さなアットホームな大学だった。正面玄関に守衛さんが居て、毎朝登校するとそこにある名簿にサインする。建物の右半分がテキスタイル&エンブロイダリー、左半分がファインアート。ファインアートには、彫刻、絵画、版画、映像、写真、ガラス等、テキスタイル&エンブロイダリーには、シルクスクリーン、染め、織り、編み、ミシン等の部屋があり、設備は至れり尽くせり充実し、朝から夜遅くまで自由に使えた。テキスタイルの学生が、ヌードスケッチをしたければファインアートの方へ行けば良いし、ファインアートの学生がシルクスクリーンを使いたければテキスタイルの方へ来る。彼らはテキスタイルの学生とは異なった発想でシルクスクリーンを使いこなす。例えばコラージュした写真製版のシルクスクリーンに、直接タワシで傷つけて新しい表現方法を模索したりする。校内の購買部には、他学科の目新しい材料があり、小さな食堂には、ビター片手に熱い芸術論戦があった。当然の結果として、素材も技法も複合化した新しい作品が生まれる。彫刻やテキスタイル等の垣根が取り払われ、各々の表現の為に自由に素材や技法が使われ、バリアフリーなコラボレーション、これは正に20世紀後半の現代美術史そのままを体現した現場であった。教官は援助者であり、テクニシャンは技術的にも体力的にも学生の作品制作に欠かせないサポーターであった。学生生活は、各自10坪ほどのステュディオというスペースが与えられ、課題に追われることもなく、作家の様な制作三昧の日々を送る。 私は、テキスタイル&エンブロイダリーで最初の日本人留学生だったので、私の行動は、「日本人はそうするの?」とよく問われて、窮屈さと戸惑いを感じた事をのぞけば、自分に厳しく、自分を見つめ、いかに自分らしい自分にしか出来ない作品をつくるかと言う、本当に充実した時間に徹することの出来る毎日だった。 ひとことにテキスタイルと言っても、各大学それぞれに、はっきりと特色があった。学生生活も、そこから生まれる作品も全くと言ってよい程、異なったスクールカラーを持っていて、就職に有利なカレッジ、デザイナーを輩出するカレッジ、教育者を養成するカレッジ等々、ゴールドスミスカレッジは、コンテンポラリーアートそのものであった。私にとって、「水を得た魚」何物にも変えられない本当に有意義な、将に求めていた大学であった。 私の帰国後、サッチャー政権は、エデュケーションカット政策を断行した。大学の統廃合が行われ、教官の多くが大学を去り、設備は最小限にカットされた。ゴールドスミスの芸術学部は、ミラードビルディングを去りマンモス校の本校の地に戻された。教師も設備も最高に良い環境の時に私は在籍することが出来た。私と同時期にゴールドスミスで学んでいた人が多数、現在、国際展で活躍している。充実した教育現場から国際的なアーティストが育つことを、又、国の経済や政策が結果としてアートに大きく関わる事を身をもって知った。 帰国後、孤軍奮闘の日々が始まり今日に至っている。精一杯自分らしい作家活動を続けて30年余となる。人真似をした事はない。自分に出来る事、自分にしか出来ない事、それが作品制作のポリシーの一つになっている。本来、作家活動に100%邁進したい貴重な時間とエネルギーを、ボランタリー精神のみで、英国62グループの日本での作品展の開催をプロデュースしたりするのは、草分けの人間の宿命なのかも知れない。テキスタイル、エンブロイダリーを大学で学んでも卒業後に活動の場が無い事から、作品発表の為に刺繍の教官達が1962年にグループを結成したので62グループという。創設当初のメンバーは全て刺繍作家あった。1970年代の英国の芸術教育環境が充実していた結果として、刺繍技法にとどまらず多彩に展開され1980年代の質は、その内容、素材や技法のバリェーション、作品レベル、全ての点で目を見張る素晴らしいものが多数見うけられ、「手芸からアートへ」が達成された。1990年代に入ると、刺繍がバックグランドの作家は少なくなり、グループ名もテキスタイルアーティストと言うようになった。刺繍畑出身の私は、一抹の淋しさを感じている。しかしそれは、政治、経済、社会背景に裏打ちされた20世紀末現代美術の潮流そのものでもある。 私は、布を用いて冥想空間をつくり作家活動を展開してきた。インスタレーションと言う言葉が未だ日本に無かった時、「これ何?」と問われてばかりで、芸術的な評価は何も与えられなかった。しかし、私はその度に確実に、自分の中に手応えを感じ、その中の何点かの作品は、私自身のマスターピースに育っている。アートとしての作品展開を目指しているが、テレビ局や舞台美術の仕事も多い。雰囲気づくりや舞台の背景ではなく、企画、演出、音楽、美術、ダンサーや役者、全てが一丸となった芸術作品に携わりたいと念じている。 一方、私は布と糸の力を充分に引き出したオリジナルスカーフをつくり販売している。アートを目指している私にとって、長い間、スカーフの製造販売は苦痛そのものであった。精魂込めたアート作品発表の別室でのスカーフ販売は、私にとって屈辱的なことであった。しかし、1995年、あの阪神大震災によって変わった。生活も変わった。自分のアトリエ一軒を丸々失ったが、国からも県からも市からも一文の援助も無かった。国家は国民を見捨てた。幸い家族は無事だった。多くの破壊と死を目のあたりにして、「生かされている」という思いが大きかった。精神的にも又、生活造形美という観点からも、私の中にバリアフリー化が生じ、色々なパーツに別れていた私は、一つになっていった。『レクイエム・フォレスト16』は、私の商品であるスカーフによる冥想空間作品である。一枚一枚はスカーフだが、作品全体を観た時はもはやスカーフではない。フォレスト16は私の内なる革命的作品となった。昇華できたとでもいう感覚で、これ以降、スカーフ販売を屈辱と感じた事は一度もない。 東京で何年もつづいているテキスタイルのグループ展に、自信作の小作品を出品した。形がポシェットだったので、肩紐の部分を見せずに器の様に展示され、「とても良いテキスタイル作品なのに残念だ」と画廊の人に言われ、それ以降そのグループ展から外された。用のあるものは、アートスペースに展示したくないという判断である。現実社会では、工芸も美術も共に創造の世界としてバリアフリー化が進んでいる。もし、ピカソのポシェット作品であったら画廊はどんな判断をするのだろう、陳列しないのだろうか。 何がアートかということは、個々の哲学、個の人間としての存在そのものへの問いかけであると思う。1980年、英国ビクトリア&アルバート博物館で、三宅一生氏の「一枚の布」シリーズの大きな真っ赤な貫頭衣を観た時、アートとして素直に受けとめることができた。しかし90年代、海外の美術館での三宅一生展の開催を、私はアートとしてとらえる事が出来なかった。ファッションデザイナーは、創造の世界の人であるが、ファッションは、私にとってアートではない。この何とも矛盾する説明しがたい皮膚感覚を大切に、私にとっては、とても崇高な「アート」を求めて、作家活動を続けている。 2001年7月記 |